
税理士になるまでに、お金がどれくらいかかるのか気になりますね?
この記事では「税理士資格を取るまでに予備校・大学院の学費がいくらかかるのか?」について解説します。
ちなみに、税理士試験に独学で挑戦するのはおすすめできません。
独学をおすすめしない理由については「税理士試験の独学が「無理ゲー」だと思う5つの理由」で詳しく解説しています。
これから税理士を目指したいという方はぜひ最後までお読みください。
僕の実体験をもとに誰よりも詳しく解説しました!
学費の総額は約35~446万円

結論から言うと、税理士資格を取得するまでにかかる予備校や大学院等の総額は約35~446万円です。
費用にものすごく幅がある理由は、税理士になる方法として「①官報合格」と「②大学院免除を利用する方法」の2パターン存在するからです。
では、それぞれのケースで解説します。
方法①:「官報合格」年1回の税理士試験に合格する方法
年1回(8月)実施される税理士試験において、全11科目のうち5科目(会計科目2科目、税法科目3科目)に1科目づつ地道に合格する方法です。
この方法で税理士になると「官報」に合格者の名前が掲載されるので「官報合格」と呼ばれています。
受験科目の中には「受験資格が必要な科目」「必須科目」があるので注意が必要です。
| 1 | 簿記論 | どちらも必須科目 | 会計科目(受験資格なし) |
| 2 | 財務諸表論 | ||
| 3 | 法人税法 | どちらか1科目必須 | 税法科目(受験資格が必要) |
| 4 | 所得税法 | ||
| 5 | 相続税法 | 選択科目 | |
| 6 | 消費税法 | ||
| 7 | 酒税法 | ||
| 8 | 国税徴収法 | ||
| 9 | 住民税 | ||
| 10 | 事業税 | ||
| 11 | 固定資産税 |
「税法科目の受験資格の取得方法」については、こちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」で詳しく解説しています。
この組み合わせが人気となる理由は、実務での利用頻度の高さからです。
税理士試験は1度に5科目すべてに合格する必要はありません。
なので1年に1科目ずつ受験することも可能です。
また、1度合格した科目に有効期限はありません。
ですので、たとえ10年、20年かかろうとも最終的に5科目そろえばOKです。
方法②:大学院での科目免除を利用する方法
年1回の税理士試験で科目合格を積み重ね、さらに大学院を卒業することで税理士試験科目の一部分を免除してもらう方法です。
大学院に進学して税法や会計学に関する修士の学位を取得すると、以下の免除が受けられます。
- 会計学に関する大学院なら「会計科目1科目が免除される」
- 税法に関する大学院なら「税法科目2科目が免除される」
例えば、あなたが「税法に関する大学院」を卒業した場合、「税法2科目が免除」されます。
したがって、税理士試験で「会計2科目(簿記論・財務諸表論)」と「税法1科目(どの税法科目でもOK)」に合格すれば合計5科目そろうことになります。
官報合格するまでにかかる予備校の費用
では、税理士試験で地道に1科目ずつそろえる、官報合格を目指す場合の費用を考えてみましょう。
「1科目の取得に2年かかる」ことを前提として計算してみました。
税理士試験では、2年で1科目に合格できれば、まずまずのペースと言われています。
その他の計算根拠については以下の通りです。
- 取得する科目
「簿記論」「財務諸表論」「法人税法」「相続税法」「消費税法」
※最も人気の高い科目の組み合わせです。
- 利用する予備校・通信講座
①「資格の学校TAC」「資格の大原」の通学講座
②「資格の学校TAC」「資格の大原」の通信講座
③「スタディング」の通信講座
※「社会人におすすめの予備校・通信講座4選」で僕がおすすめしている予備校・通信講座です。
★1年目・2年目について
「資格の学校TAC」と「資格の大原」については
1年目 初学者用のカリキュラムを選択
2年目 経験者用のカリキュラムを選択
「スタディング税理士講座」については初学者、経験者によってカリキュラムの違いはありません。また、簿記論と財務諸表論はセットになっており1科目づつの受講はできません。
.png)
| 合格までにかかる予備校の費用 | |
| スタディング | 350,812円 |
| 資格の大原(WEB通信) | 1,958,000円 |
| 資格の大原(通学) | 2,108,000円 |
| 資格の学校TAC(WEB通信) | 2,125,000円 |
| 資格の学校TAC(通学) | 2,125,000円 |
ただし、「資格の学校TAC」と「資格の大原」については
- 複数科目の申し込み
- 2年目も継続して申し込み
などで受講料が割引になりますので、実際は10%ほど安くなるのではないかと思います。
スタディングは税理士試験の通信講座の中では最安値。
スタディングは「コスパの良さ」「スマホで勉強できる」という点が評価され、社会人を中心に利用者が急増している人気の通信講座です。

KIYOラーニング㈱IR情報より引用
⇒【スタディング体験談】仕事や育児のスキマ時間で勉強して簿財2科目合格!
\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /
今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)
【15%割引後の価格(税込)】
・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)
・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)
しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。
もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!
無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。
今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】
10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。
大学院での科目免除を利用した場合にかかる予備校・大学院の費用
先ほどご説明したように、大学院を卒業すると科目免除を受けることができます。
- 会計学に関する大学院なら「会計科目1科目が免除される」
- 税法に関する大学院なら「税法科目2科目が免除される」
今回は「税法に関する大学院を卒業して税法2科目免除」を前提として費用を計算します。
理由は、「税法2科目免除」のみを利用する人が圧倒的に多いからです。
費用の計算については次の条件で行っています。
- 取得する科目
「簿記論」「財務諸表論」「消費税法」
※最も人気のある科目の組み合わせで、「消費税法」は全11科目中3番目の受験者数です。
消費税法についてはこちらの記事「【税理士試験】消費税法の難易度・合格率推移は?」も参考にして下さい。
- 利用する予備校・通信講座
①「資格の学校TAC」「資格の大原」の通学講座
②「資格の学校TAC」「資格の大原」の通信講座
③「スタディング」の通信講座
※「社会人におすすめの予備校・通信講座4選」で僕がおすすめしている予備校・通信講座です。
★1年目・2年目について
「資格の学校TAC」と「資格の大原」については
1年目 初学者用のカリキュラムを選択
2年目 経験者用のカリキュラムを選択
「スタディング税理士講座」については初学者、経験者によってカリキュラムの違いはありません。また、簿記論と財務諸表論はセットになっており1科目づつの受講はできません。
★大学院について
最も学費が安いと思われる「地方国立大学」と、一番学費が高い「明治学院大学大学院」を例として計算しています。
※入学から卒業までの2年間にかかる入学金・授業料の合計金額です。
.png)
★最安値「スタディング+地方国立大学」
183,656円+1,353,600円=1,537,256円
★最高値「TAC+明治学院大学大学院」
1,190,000円+3,270,000円=4,460,000円
税理士試験を受けるにも費用がかかる
税理士試験の受験は無料ではありません。
受験にかかる費用は以下の通りです。
| 申込む科目数 | 受験手数料 |
| 1科目 | 4,000円 |
| 2科目 | 5,500円 |
| 3科目 | 7,000円 |
| 4科目 | 8,500円 |
| 5科目 | 10,000円 |
(出典:国税庁HP)
受験手数料は、税理士試験の願書に「収入印紙」を貼り付けることで支払います。
税理士登録にも費用がかかる
税理士登録を行って、初めて税理士を名乗り、税理士業務を行うことができます。
その税理士登録にも費用がかかります。
- 登録手数料 5万円
- 登録免許税 6万円
- 所属する税理士会に払う入会金 約5万円
- 所属する税理士会に払う年会費 約10万円
税理士登録した年は総額で約26万円の費用がかかります。
それ以降は、毎年税理士会の年会費が約10万円かかります。
税理士試験は何月に実施される?
税理士試験は、1年に1回、毎年「8月」に実施されます。
過去の実施状況を見ると、2012年(平成24年)のみ1日目が7月31日になっていますが、それ以降は毎年8月に実施されています。
| 回 | 実施年 | 月・日・曜日 |
| 第62回 | 2012年(平成24年) | 7月31日(火)~8月2日(木) |
| 第63回 | 2013年(平成25年) | 8月6日(火)~8月8日(木) |
| 第64回 | 2014年(平成26年) | 8月5日(火)~8月7日(木) |
| 第65回 | 2015年(平成27年) | 8月18日(火)~8月20日(木) |
| 第66回 | 2016年(平成28年) | 8月9日(火)~8月11日(木) |
| 第67回 | 2017年(平成29年) | 8月8日(火)~8月10日(木) |
| 第68回 | 2018年(平成30年) | 8月7日(火)~8月9日(木) |
| 第69回 | 2019年(令和1年) | 8月6日(火)~8月8日(木) |
| 第70回 | 2020年(令和2年) | 8月18日(火)~8月20日(木) |
| 第71回 | 2021年(令和3年) | 8月17日(火)~8月19日(木) |
| 第72回 | 2022年(令和4年) | 8月2日(火)~8月3日(水) |
| 第73回 | 2023年(令和5年) | 8月8日(火)~8月10日(木) |
| 第74回 | 2024年(令和6年) | 8月6日(火)~8月8日(木) |
なお、税理士試験の申込用紙の配布は毎年4月の中旬から始まります。
申込期間は毎年5月上旬~中旬です。
税理士試験は1年に1度しか実施されないので、申込手続きの失敗は許されません。
国税庁のHPでスケジュールを必ずチェックする必要があります。
税理士はどうやってなるの?
前述したように、税理士になる方法としては主に「①官報合格」と「②大学院免除を利用する方法」の2パターンがあります。
僕は30歳から税理士を目指し始めたので、少しでも早く、確実に税理士資格を取ることを希望していました。
ですので、「②大学院免除を利用する方法」を選択しました。
僕の実体験に基づき、社会人から税理士になる方法をこちらの記事「社会人が最短で税理士になるための完全ロードマップ」にまとめました。
少し長い記事ですが、かなり具体的に書いているので参考になると思います。
まとめ
・最も費用が高いのは、TACの通学講座を受講して、大学院(明治学院大学)で税法2科目免除を受ける方法で(約446万円)
この結果を見ると、スタディング税理士講座で官報合格を目指すのが一番良さそうに思えます。
スタディングなら少ない費用負担で、しかも仕事のスキマ時間を利用して税理士になれるので最高です!
しかし、実際に官報合格にたどり着ける人は少なく、大学院での免除を利用する方が多いのが現実です。
しかも、官報合格までには約10年という長い期間がかかってしまうことも珍しくありません。
ですので、コスト面だけで取得方法を選択するのはおすすめできません。
取得方法を選ぶ際は「年齢」「家庭環境」「資金」「勉強時間が確保できるか」など総合的な判断が必要となります。







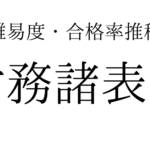

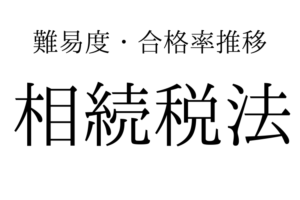
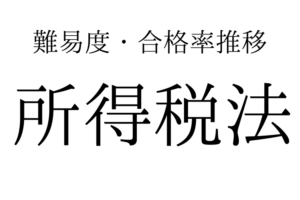

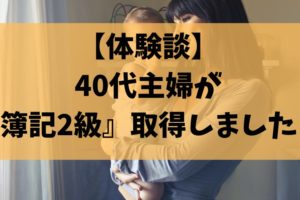





の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す