はじめまして、はらすけです。
僕は限りなくブラックに近い中小企業を退職後、30歳から勉強を始めて約6年で税理士になりました。(詳しい自己紹介はコチラ)
将来、AI(人工知能)に代替される仕事ランキングには「経理事務」「税務申告書作成」が軒並み上位にランクインされています。
この2つの業務は、税理士の仕事内容の根幹となるものです。
ではAIの進化によって、本当に税理士の仕事が将来なくなるのでしょうか?
結論から言うと「税理士の仕事は無くならない」です。
税理士の仕事がなくならない理由について、3つの視点から考えてみたいと思います。
理由その①決算書の信頼性を確保できない

税理士の仕事の中で大きなウエイトを占めているのが、企業や個人事業主等の代わりに会計帳簿や決算書を作成するという仕事です。
しかし、近年「FinTech(フィンテック)」と呼ばれる金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動きが活発化しています。
具体的な例をあげると、銀行が持っている銀行取引データ(通帳の動き)を自社の会計システムに連携させたりする技術です。
このフィンテックにAI技術を組み込むことで、会計帳簿の大半をコンピューターに自動作成させることが可能になります。
今後、AI技術の進化によって、帳簿作成にかかる「作業量」が大幅に削減されることは間違いないと思います。
ただし、ここで問題となるのが出来上がった「会計帳簿や決算書の信頼性」です。
多くの中小企業は金融機関からの融資を受けています。
企業は融資を受ける際、必ず金融機関に「決算書」を提出します。
金融機関は企業から提出された決算書の情報に基づき数千万円、数億円の融資を実行できるかどうかの判断を下します。
したがって、金融機関にとって企業から提出された決算書が、会計ルールによって正しく作成されているということが非常に重要となります。
もしも、あなたが銀行の立場なら次のどちらの決算書を信頼するでしょうか?
- 経営者がAIで自作した決算書
- 会計の専門家である税理士が作成に関与した決算書
当然、②「会計の専門家である税理士が作成に関与した決算書」の方を信頼するでしょう。
いくら経営者がAIを駆使して決算書を作ったとしても、所詮素人が作成した決算書。
それを信じて大金を融資するのは、金融機関としてもリスクが大きいです。
また、金融機関独自で企業から提出された決算書が適正かどうかの判断をすることは非常に困難です。
したがって、会計の専門家からのお墨付きを受けた決算書を要求するのは当然なのです。
経営者にとっても、必要な時に融資が受けられないということは、会社の存亡にかかわる大問題。
このように、AI技術は会計帳簿の作成にかかる「作業」を代替することはできますが、作成した決算書に「信頼性」を与えることはAIにはできません。
理由その②日本の税金制度は複雑すぎる

日本では納税者(個人や企業)は税金を自分で計算して申告し、国に納付するという「申告納税制度」が採用されています。
これは所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などで採用されています。
では実際に、自分の納税額をスラスラと計算して申告納付できる人がどれだけいるでしょうか、、、?
ほとんどいないというのが現実です。
では、なぜそうなってしまうのか?
理由は簡単で、日本の税制があまりにも「複雑すぎる」からです。
仮にあなたがAIに税金を計算させたとしましょう。
その計算された税額に納得して、すんなり納付することができるでしょうか?
あなたが高所得者でAIが算出した所得税額が「500万円」だった場合、必ずこう思うはずです。
- 本当にこの税額で合っているのだろうか?
- もしかすると計算が間違っているんじゃないのか?
- 税理士に相談すれば、もっと安くなる方法があるかもしれない!
税制が複雑すぎるあまり、「AIが算出した税額が妥当な金額なのか?」「税金が最も安くなるように計算されているのか?」といったことが納税者自身で判断できないのです。
このように税制が複雑である限り、「税理士」という税金の専門家としての仕事はなくなりません。
理由その③税理士は経営者の相談相手である
 中小企業の経営者は365日仕事のことを考え、常に重い責任を抱えています。
中小企業の経営者は365日仕事のことを考え、常に重い責任を抱えています。
しかも、相談相手も少なく孤独な毎日を送っています。
そんなとき、毎月巡回監査に来る税理士が経営者にとっての良き相談相手になっているケースは少なくありません。
会計・税務・経営に関すること以外にも、プライベートの悩みなどを相談することもしばしばあります。
会話することで気持ちを元気にさせてくれるような税理士は、孤独と闘う経営者にとって無くてはならない存在でしょう。
当然ですが、このような仕事はAIが代替することはできません。
税理士の仕事が大幅に減少する可能性がある2つのケース
将来、税理士の仕事がなくなる可能性は低いです。
しかし、税制に大きな改正が入ると状況は違っていきます。
ケース① 税金制度が超シンプルになる
税制が超シンプルになると税理士の仕事は激減する可能性があります。
例えば、その年の儲けに対して一律で一定の税率かかけて税金を計算するといった改正が行われた場合です。
- 「年収×30%=税金」(サラリーマンの場合)
- 「利益×30%=税金」(企業や個人事業主の場合)
税金の計算方法が簡単になると、納税者自身が自分の納税額を計算できます。
税制が超シンプルになると、税理士が出る幕はほとんど無くなるかもしれません。
ケース② 賦課課税方式に移行する
「賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)」が導入されると税理士の仕事は激減します。
賦課課税方式とは「固定資産税」「自動車税」などに採用されている方式で、国や都道府県、市区町村があなたの税金を代わりに計算して通知してくれる方式です。
今後、マイナンバー制度やキャッシュレス化が浸透すれば、税務署が個人や企業のお金の流れを把握しやすくなります。
そうすれば、賦課課税制方式に移行することも可能になるかもしれません。
国等が税金の計算をして、納税者に通してくれる仕組みが実現すれば、税理士が出る幕はなくなります。
最後に
AI技術の発展によって会計帳簿作成などの「作業」は大幅に減少することが想定されます。
しかし、決算書や税金申告書へ「信頼性」を与えたり、経営者からの相談に対応するといった業務は、今後もAIに代替される可能性は低いです。
ただ、AIの進化よりも「税制の簡素化」が進むことの方が、税理士の仕事に与える影響がはるかに大きいものと考えられます。
最後までお読みいただきありがとうございます。



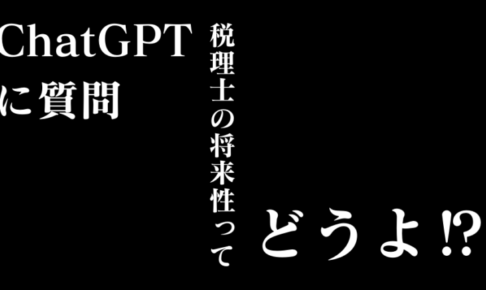




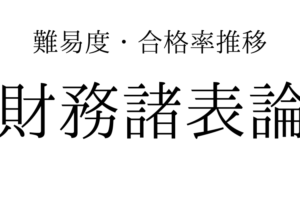


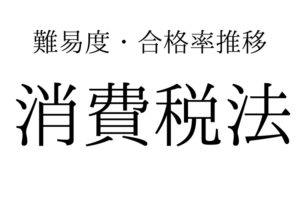

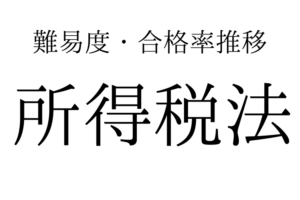

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す