相続税法の難易度「★★★★☆」
相続税法の難易度は高めの「4」です。
相続税法の学習ボリュームは、法人税法、所得税法に次ぐ多さとなっています。
問題構成は理論問題が50%、計算問題が50%となっています。
「相続税法」では相続税と贈与税の2つの学習範囲があるのが特徴です。
相続税は亡くなった人の財産を引き継ぐ(相続する)人が払う税金です。
贈与税は誰かから財産をもらった時に払う税金です。
全国で相続税の納税が必要な人は約8%と言われており、一部の富裕層にしか関係ない税金といえます。
件数が少ないとはいえ、相続税の申告で税理士が得る報酬はかなり高額になるケースもあります。
また、将来の相続税対策として資産家に金融商品や不動産を斡旋することで得る「手数料」も高額です。
今後の実務を考慮すると、ぜひ取得しておきたい科目だと思います。
また、相続税の申告は頻度が少ないこともあり「苦手」とする税理士も多いです。
そこに着目し、相続税申告に特化した税理士も増えています。
また、相続税法は税理士試験の最終科目として受ける受験生が多く、かなりの強者との競争となるので合格するのは容易ではありません。
これは税法科目全般に言えることですが、どの税法科目も科目合格をいくつか突破している受験生が多く、全体的にレベルが非常に高いです。
その中で上位約10%に入ることは至難の業。
税理士試験を終えるまでの平均期間が約10年といわれているのもうなずけます。
直近の「2023年第73回税理士試験」の受験者数と合格率は以下の通りです。
| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 2023年合格率(%) | 受験者数占有率(%) | |
| 簿記論 | 16,093 | 2,794 | 17.4 | 34.3 |
| 財務諸表論 | 13,260 | 3,726 | 28.1 | 28.2 |
| 所得税法 | 1,202 | 166 | 13.8 | 2.6 |
| 法人税法 | 3,550 | 497 | 14.0 | 7.6 |
| 相続税法 | 2,428 | 282 | 11.6 | 5.2 |
| 消費税法 | 6,756 | 802 | 11.9 | 14.4 |
| 酒税法 | 463 | 59 | 12.7 | 1.0 |
| 国税徴収法 | 1,646 | 228 | 13.9 | 3.5 |
| 住民税 | 462 | 68 | 14.7 | 1.0 |
| 事業税 | 250 | 41 | 16.4 | 0.5 |
| 固定資産税 | 846 | 146 | 17.3 | 1.8 |
| 合計(延人員) | 46,956 | 8,809 | 18.8 | 100 |
(出典:国税庁HP)
「相続税法」は、「簿記論」「財務諸表論」「消費税法」「法人税法」に次ぐ5番人気となっています。
また、直近6年の相続税法の受験者数は以下のように推移しています。
| 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | |
| 簿記論 | 16,093 | 12,888 | 11,166 | 10,757 | 11,784 | 11,941 |
| 財務諸表論 | 13,260 | 10,118 | 9,198 | 8,568 | 9,268 | 8,817 |
| 所得税法 | 1,202 | 1,294 | 1,350 | 1,437 | 1,659 | 1,704 |
| 法人税法 | 3,550 | 3,454 | 3,532 | 3,658 | 4,260 | 4,681 |
| 相続税法 | 2,428 | 2,370 | 2,548 | 2,499 | 2,897 | 3,089 |
| 消費税法 | 6,756 | 6,488 | 6,086 | 6,261 | 7,451 | 7,859 |
| 酒税法 | 463 | 454 | 470 | 446 | 492 | 546 |
| 国税徴収法 | 1,646 | 1,709 | 1,702 | 1,629 | 1,677 | 1,703 |
| 住民税 | 462 | 476 | 378 | 381 | 410 | 460 |
| 事業税 | 250 | 269 | 302 | 335 | 392 | 418 |
| 固定資産税 | 846 | 910 | 941 | 874 | 868 | 845 |
| 合計 | 46,956 | 40,430 | 37,673 | 36,845 | 41,158 | 42,063 |
相続税法の合格率推移
直近11年間の相続税法の合格率推移(緑色の線)は以下の通りです。
.jpg)
全11科目全体の合格率と比較すると「やや低め」の合格率で推移しています。
\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /
今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)
【15%割引後の価格(税込)】
・相続税法アドバンスパック定価63,800円 ⇒ 54,230円(9,570円お得!)
・冊子オプション付き 定価83,600円 ⇒ 71,060円(12,540円お得!)
しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。
もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!
無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。
今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】
10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。
まとめ
相続税法は実務での利用頻度も高く、できれば受験しておきたい科目の1つです。
相続税に特化すれば、他の税理士との差別化にも繋がりますし、相続税対策として金融商品や不動産を斡旋することで得る「手数料」も期待できるので、大きく稼げる可能性があります。
また、税法科目特有の「条文の丸暗記」がどうしても苦手な方は、大学院での税法2科目免除も選択肢に入れると良いかもしれません。





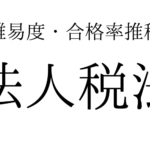
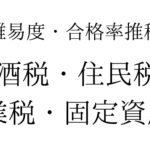




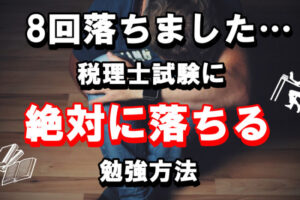
実施の-第71回税理士試験-の日程を大予想!-300x200.jpg)
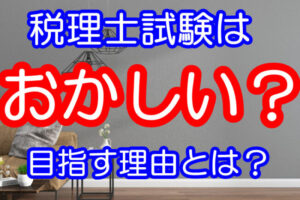
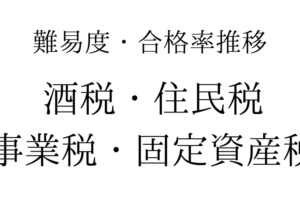

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す